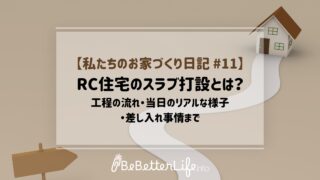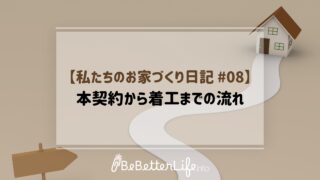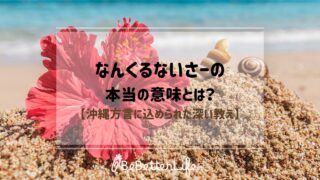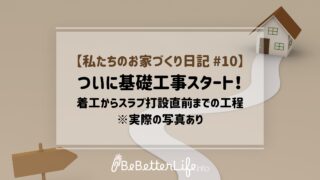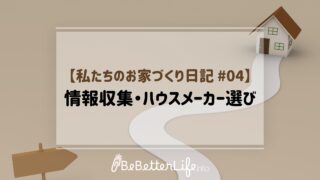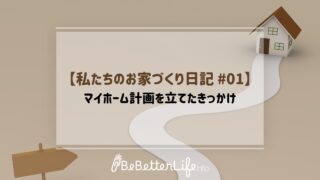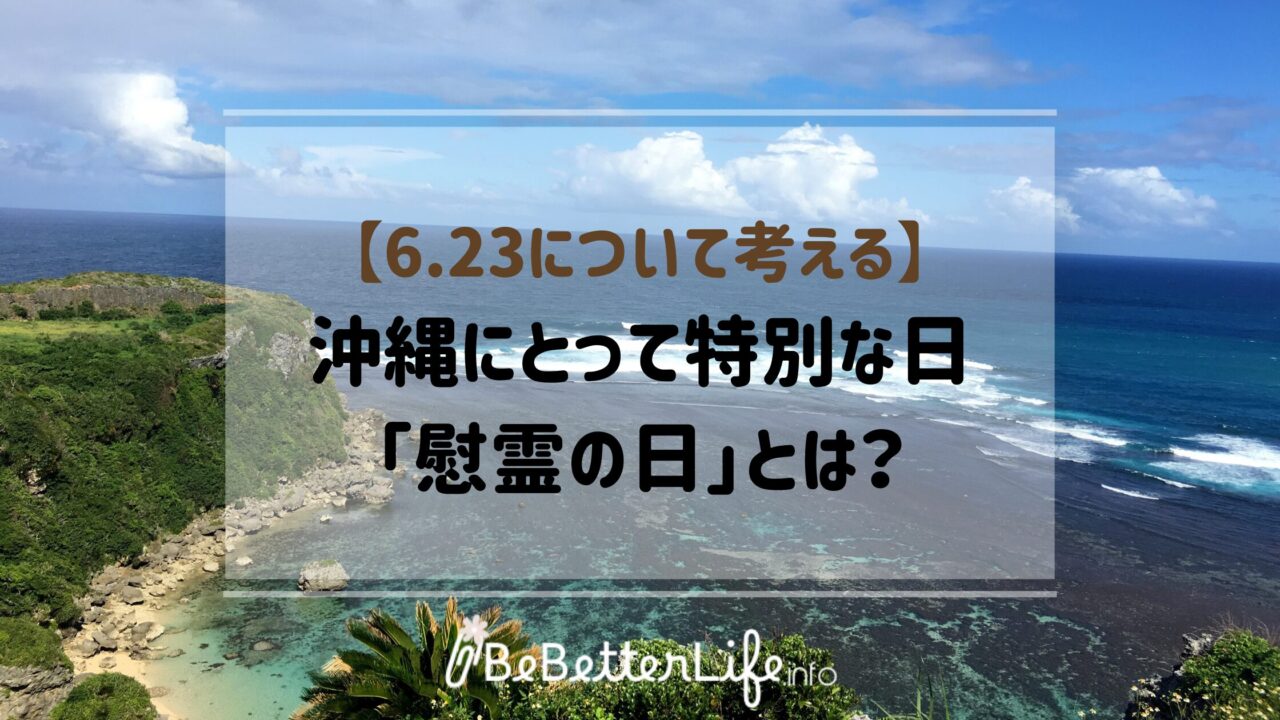
はじめに|慰霊の日とは?
慰霊(いれい)日 は、沖縄戦の戦没者を追悼し、恒久の平和を祈る日です。
1945年6月23日、沖縄戦における日本軍の組織的な戦闘が終わったとされており、その日が慰霊の日と定められました。
沖縄県では、この日を公式な記念日としており、県条例により、県内の学校や職場は祝日となります。
慰霊の日は、沖縄県にとって重要な日で県民の心に深く刻まれており、毎年、沖縄県糸満市の平和祈念公園*で全戦没者追悼式が行われます。
平和祈念公園の正式名称は、沖縄県営平和祈念公園。沖縄戦終焉の地となった沖縄本島南部の糸満市摩文仁(まぶに)にあります。約40ヘクタールの広大な公園内には、国立沖縄戦没者墓苑や各都道府県の慰霊塔・碑があり、戦没者への慰霊を捧げるとともに、平和の礎・平和祈念堂・平和祈念資料館などを通じて平和の尊さを体感する場所です。平和祈念公園内には4つのゾーン(平和ゾーン、霊域ゾーン、平和式典ゾーン、園路広場ゾーン)があり、そのなかでも最も多くの観光客が訪れる場所が平和ゾーンです。平和ゾーンには、沖縄戦終結50周年の1995年に建てられた「平和の礎(いしじ)」や、戦没者の鎮魂と恒久平和を祈る「沖縄平和祈念堂」、沖縄戦に関する資料が展示された「沖縄県平和祈念資料館」などがあります。
なかでも、「平和の礎」には、国籍や軍人、民間人の区別なく、沖縄戦などの戦没者の氏名が刻銘されており、沖縄の風土と歴史の中で培われた「平和のこころ」を感じられます。「平和の礎」は、「鉄の暴風の波濤が平和の波となってわだつみ(海神)に折り返して行く」というコンセプトで、海に面した平和の広場を中心とし放射線状に配置されています。
(引用:『沖縄・平和祈念公園で平和を体感する』- たびらい)

沖縄県民にとってこの日が特別な理由
沖縄県では、毎年、小学校のうちから平和学習の一環として「沖縄戦」のことを深く学びます。
インターネットや資料で沖縄戦について調べるだけでなく、自分の住んでいる地域での当時の様子を戦争体験者からお話を伺ったり、自分のオジー・オバーにインタビューをしたり、沖縄戦で使用していたとされるガマ*へ行ってその場に触れ当時の様子を想像したり。
戦争の悲惨さや命の尊さを直接聞いて、その場に足を運んで感じて、学んできました。
二度と沖縄が、日本が、地獄のような戦場にならないように、そして悲惨な戦争を繰り返さないように、戦争体験者たちを中心に下の世代へ語り継がれています。
沖縄方言で「ガマ」は洞窟を意味します。ガマは、戦時中、米軍の攻撃から身を守るため、住民や日本兵が避難場所、野戦病院、陣地豪として利用した自然洞窟のことです。
ガマは、沖縄戦の悲惨さを物語る「もの言わぬ語り部」として、今も存在しています。
今、沖縄から伝えたいこと|大人になった私が今思うこと
小・中・高・大学時代、私は何度も沖縄戦について学びました。戦争の恐ろしさや悲しさを「知っているつもり」でした。
でも、結婚して子どもを授かり、母親として慰霊の日を迎えるようになってから、戦争への感じ方が変わりました。
戦地に向かった男性たちの苦しさだけではなく、家族を守ろうとした女性たちや、何もわからないまま巻き込まれた子どもたちの苦しさにも、想いを馳せるようになりました。
例えば、生まれたばかりの赤ちゃんがいる家庭では、オムツはどうしていたのか。お母さんたちは水もろくに飲めない中、母乳を与えることはできたのだろうか。小さい子どもたちは、空腹や不安にどれだけ耐えたのか——。
今、自分の子どもたちと過ごす日常のなかで、そんな疑問が次々に浮かびます。そして、今の私たちがどれだけ恵まれているか、身にしみて感じます。
私の母方のオジー・オバーも、父方のオジー・オバーも、沖縄戦のことは「二度と思い出したくない」と一切語りませんでした。だから私は、自分の祖父母からは直接戦争の話を聞けないまま育ちました。
父方のオジー・オバーはすでに天国へ。母方のオバーも昨年、旅立ちました。今生きている母方のオジーは91歳ですが、認知症のため、もう戦争の記憶を語ることはできません。
今年で沖縄戦から80年。
体験者の平均年齢は87〜90歳といわれ、直接話を聞ける「最後の時代」になりつつあります。
つらい記憶を乗り越えて、語り継いできてくれた先代たち。けれど、もうその声は、少しずつ小さくなってきました。
だからこそ、次に語り継ぐのは、私たちの役目です。戦争を経験していない私たちが、聞いた話、学んだこと、感じたことを、次の世代へ伝えていく。それが、私たちにできる平和への行動なのだと思います。
今の子どもたちは、物に恵まれ、安全で、自由に学びながら育っています。だからこそ、戦争のない世界がどれほどありがたいものなのか、実感しづらいのかもしれません。
でも、私たちは忘れてはいけません。あの時、頑張って生き抜いて、命を繋いでくれた先代のおかげで今の私たちは生かされています。
私たちは、それを子どもたちへ伝えていく必要があります。
沖縄には、こんな言葉があります。
命どぅ宝(ぬちどぅたから)
命こそ宝
この言葉を、ただの合言葉にしないために。私たちは、今を生きる子どもたちへ、そして未来へ、命の尊さと平和の大切さを伝え続けていきたいと思います。
慰霊の日の過ごし方
1. 黙祷(もくとう)をする
正午(12時)に1分間の黙祷をしよう。この日は、家庭、職場、学校、道端でも、手を合わせる人が多いです。
2. 平和祈念公園や慰霊碑を訪れる
「平和祈念公園」や「魂魄の塔」などに足を運び、献花やお線香を手向けます。人混みを避けて、近所の慰霊碑を訪れる方も多いです。
3. おうちで祈る・手を合わせる
仏壇の前で、沖縄戦で亡くなった方々の冥福と平和を祈る。家族みんなで静かに手を合わせ、平和について話す時間にする。
4. 家族や子どもと戦争の話をする
祖父母の話を聞く。本や絵本、ドキュメンタリーを一緒に観て、命や戦争について話す。子どもにとっては、命の大切さを考える貴重な時間になります。
5. テレビやラジオで式典や特番を見る
NHKや沖縄のローカル局で、平和祈念式典が中継されます。戦争体験者の証言、特集番組などを視聴しながら静かに過ごす家庭も。
7. SNSやブログで平和への想いを発信する
個人の体験や想いをシェアし、「今、私たちにできること」を考える日として過ごす。若い世代が発信することで、語り継ぐ役目を果たすことにもつながります。
まとめ
沖縄県民にとって、「慰霊の日」はとても特別な日でこれからも大切にしていきたい日です。
これまでつらい記憶を乗り越えて、語り継いできてくれた先代の方たちの平均年齢も高齢になり、戦争体験者の語り手の声が小さくなってきているのが現状です。
だからこそ、次に語り継ぐのは、私たちの役目です。
戦争を経験していない私たちが、これまで聞いた話、学んだこと、感じたことを、次の世代へ伝えていくことが、平和への第一歩になると信じています。
▶︎コチラの記事もオススメです:【6.23について考える】沖縄戦をテーマにしたおすすめの曲4選

参考
『慰霊の日』- Wikipedia
Who wrote this article
c h u r a フリーランスライター
沖縄生まれ・沖縄中部育ち、ちょっぴりアメリカナイズされた沖縄在住の4児ママです!沖縄ならではの”ちゃんぷる〜文化”と私自身のリアルな経験を交えながら、暮らしをよりbetterにする情報やライフハックを沖縄からゆる〜くお届けします!